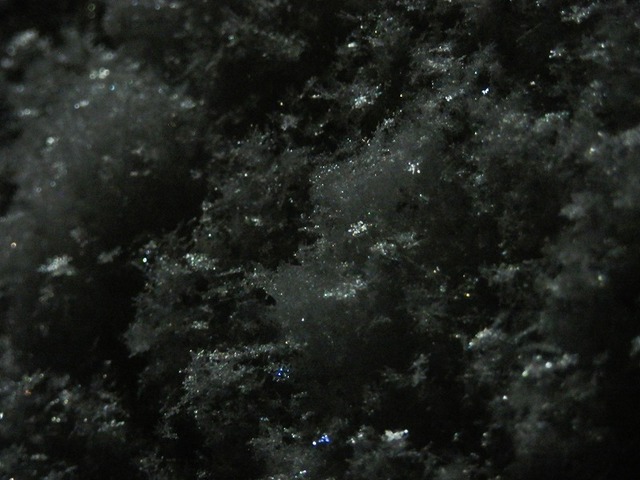時の遡上 [poem]
再掲:『ハイビスカスの憂鬱』 [poem]

時々、思い出している。 単なる郷愁ではない。 今とこれからを生きる時の踏切り板。 自分のHPをyahooで終了してしまったが、このシリーズ《昔の話をしよう。》が時々読み返したくなる。
《昔の話をしよう。》1972年。「私の詩集」と「黒・コ」の時代が過ぎ、帰郷していた。
ぼくは方向を見失いつつも二十歳になり、燃えカスに再び火を呼ぶ機会を待ち始めていた。
『ハイビスカスの憂鬱』
1972/10/30
ハイビスカスの悲しさは
その紅色の罪深さ
人々のさざめきの裏側に
ひょいと横町を曲がると
広大な海が広がる
貧弱な夢想をけちらして
冷徹に光りだす世界に
若すぎたはずの ぼく
そして あんたが
しょぼつく瞳で横顔を見せる
闇の中にひそむ
数知れない老いの影達が
突如としてシンバルを鳴らす
今日の計画を持たない
老いて行く ぼく
そして あんたが
暦の上に舌をすべらす
昨日を探す
黒いコートの男の影
横町から顔を出す
憂鬱の花々
待ってはくれない時間が
歩の悪くなった ぼく
そして あんたを
加速度的に老いへと
落としめるだろう
ハイビスカスの美しさは
その紅色の恥ずかしさ
はたち
何を見ぬいたか おまえは
何をこまぬいているのか
聞こえなくなった
花火大会のざわめきと
カーニバルの唄を
なつかしがっては 只々
生活するのは だれだ
今日の計画を持たずとも
時間は待つことをなく
未来をひきずり出してくる
何を恥らうというのか
その表通りをさけるとは
やっかいな精神という代物
捨てる訳にもゆかず
立て飢えたる あんた
そして ぼく
鬱々とした花弁の嵐
ふと見上げるイルミネーション
にじんで見えた時
立て 飢えたる ぼく
そして あんた
ハイビスカスの情熱は
その紅色の狂おしさ
つきあげてくる脈動を
ぼくは感じるだろう
歩いている並木道で
すれちがう人々の
冬の海の色をした瞳に刺されても
ぼく そして あんたは
エンピツとノートを持って
つきあげてくる紅色を
走り回りながら唄いあげる
はたち
何を見てしまったのか おまえ
考えあぐねることなく
今からでも
東の方へ向かえ
けっして旅立つことなど
信じていなくても
海へ向かえ
その横町をひょいと曲がって
なんなら
公園の前から枯れ葉を肩に
バスに乗って
立って歩き出す ぼく
そして あんた
ハイビスカスの香しきは
その紅色の空々しさ
明日はくもりのち雨か雪
足の裏側まで 照らし出す
白昼夢を持たぬ世界
三千行も続く唄を
ねそべってたどる ぼく
そして あんた
もうよしてほしい
物欲しそうに窓から
覗くのは
早く早く
雲の流れる向こうに
かけつけて行って
ぼく そして あんた
逆立ちしてでも
海を探し出さなけりゃ
少女趣味は終わった
そして
秘密結社時代も
ハイビスカスの罪深さは
その紅色の淋しさか
どこかに行けば つなぐ手が
待っている 今からでも
先へ [poem]

陽射しが僕を
膨らませて
僕は空へと浮かび上がる
寝ころんだままでスイスイと地上を見渡すように流れてゆく
あそこは16歳の頃の涙山
この下は17歳の頃の電話ボックス
ああ、ここは18歳の時の赤い橋
どんどんと景色が変わる
色とりどりのヘルメットがひしめいているのが見える公園
紫煙が漏れる下宿屋の窓
随分いろんな所をスイスイと流れてきたなぁ
時々の
猫と暮らせば
憧れるその寝顔

季節も目くるめく変わる
暗転する舞台が早変わりするように
僕は
青春を駆けて抜けた
ふわふわと浮かんでなんていられずに
切り裂くように走った。
また、
風を受けてひゅるりと
舞上がって行こうか
自転車を駆って早ずり謄写版のように号外をまき散らそうか

生きてきたあちこちを
写真にして壁に貼り付ければ
部屋は賑やかに植栽の力を漲らせるだろう

庭の花は冬を乗り切って
じっと耐えている
春の準備をしながら何食わぬふうに
鼻歌交じりに卯月の雪をかわしてゆく

僕は
生き続ける準備はできているのか
雨が僕に告げること [poem]
耳の奥に夢のノックが続き
目が覚めると
激しい雨が窓を打つ
雨が
僕を 青春へ引き戻す
どれほど濡れることも怖れず
歩き続けた反旗の日々
駆け出す者は何を掴むのか
雨が記憶の糸を打つ
もう
ドアを閉めて
傘を小脇に
歌を隠蔽して
街角を後にする
雨が僕を
晒して行く
ほら、
もう少しで消え失せて
無かったことにする
いや、
やがては雨が上がり
虹さえ小鳥たちと歌うだろう
明日は
冷たい雨が続くという
水溜まりを覗き込むと
ほら、君の長く伸びた髪がなびいて
ほら、君の弾む声が波紋を作って
雨が僕に告げること
ちょっと休憩
目が覚めると
激しい雨が窓を打つ
雨が
僕を 青春へ引き戻す
どれほど濡れることも怖れず
歩き続けた反旗の日々
駆け出す者は何を掴むのか
雨が記憶の糸を打つ
もう
ドアを閉めて
傘を小脇に
歌を隠蔽して
街角を後にする
雨が僕を
晒して行く
ほら、
もう少しで消え失せて
無かったことにする
いや、
やがては雨が上がり
虹さえ小鳥たちと歌うだろう
明日は
冷たい雨が続くという
水溜まりを覗き込むと
ほら、君の長く伸びた髪がなびいて
ほら、君の弾む声が波紋を作って
雨が僕に告げること
ちょっと休憩
新しい任地へ赴く二人へ感謝を込めて贈る言葉。 [poem]

『忘れない心に咲く向日葵』
向日葵が二輪
ふいに南風に揺れて
サトポロペツに種をまく
そのオイルは飢饉のときに役立つだろう
満面の笑みは
タブレットの画面に刻まれて
繰り返し 繰り返して 寄り添ってくれる
彼方の地から巡り来て
爽やかに たおやかに 寛大に
戸口に
窓辺に
神の家に 咲きほころびて
その笑顔が語りかけるだろう
握手しよう
抱擁しよう
見つめあおうと

向日葵が二輪
さらに北風を防いで
サトポロペツに種をまき
そのオイルは心が病むときに癒すだろう
陽を含んだ声は
謙遜な心にこだまして
繰り返し 繰り返して 寄り添ってくれる
彼方の地から巡り来て
堅固に のびやかに 惜しみなく
街路に
公園に
神の家に 葉を広げて
その歌声が手を引くだろう
感謝しよう
賛美しよう
励ましあおうと
(写真は北海道大学農場にて2013年夏)
2015/8/16 Shigesann
「十代の蹉跌」 [poem]

ペンキの剥がれた郵便受けが
ブロック塀にしっかりと据えられている。
鍵がかかったままの
「暗がり」の箱の中に
過去になっていった忘れたままの「蹉跌」が詰まっているのだ。
そして
ぼくの郵便受けには
二通の手紙が差し戻されたままになっている。
「宛先人不明」
差し出したのは
十代の終わりだったころ。

それは
住所の違う二人の「緒夢」宛て。
もう会えない、二人の緒夢へ
ささやかな人生の織り糸に「緒夢」というペンネームの二人の女性がいた。
二人ともぼくに詩を送ってくれたが、
ひとりはもう生きてはいない。
もうひとりは消息不明。
■もう生きてはいない『緒夢』へ
もういなくなってしまった「緒夢」と、強制的にさよならしたのは「緒夢」の方から。

君は、ぺろりと「自殺」してしまった。
なんで、どうして、
最高に幸せだったはずなのに。
うん、最高に幸せだったからか、ここを逃すと後は悲しみ。
今なら可能性の中で死ねるから。
「緒夢」君と出会ったのは秋の入り口の大通公園だった。
ぼくは、ガリ刷りの製本した薄い詩集「私集」を売っていた。100円。
君は旅行者だった。
すぐに打ち解けて意気投合。
「どっこ」でスパゲッティ食べて、
「B♭」に連れて行ったっけ。Jazzは小気味よくぼくらを包み込んでくれたね。
どうしてだったか、
演劇部の後輩が釧路の灯台でウィスキー飲んで寄りかかったまま凍死した話をしたんだ。
どうしてだったんだろう。
君がきっとそれを引き出すように死ぬことを話題にしたんだと思う。
だから、そんな話になったんだ。
まさか、まねして死のうとするなんて思っても見なかった。
そして、君はスケッチブックに連絡先を書いてびりりとリングから破いてくれた。
「手紙くれる?
手紙書くね。」
まだ、時代は携帯もパソコンも無かったころ。
それで、さよなら。
君は、東京へと帰っていった。
再会して半年もしないうちに見失ってしまった。

■年長の詩人『緒夢』へ
名前も変えてしまったあなたは、
兵庫へ帰って行ったきり消息はもう分からない。
あなたと会ったのは札幌オリンピックの年の冬。
けっこう雪が多かった。
当時はまだ、歩道の除雪がままならなくて
でこぼこの雪の上を歩いて行き
繁華街を外れた、心地良い喫茶店で友人たちに紹介された。
感性の豊かなあなたは
ぼく、および僕らを魅了してしまったね。
そして、
ぼくへの詩を載せた
詩集を置いて
みんなの前から
「かまいたち」みたいに、いくらかの切り傷を残して
消えてしまった。
十代の蹉跌。
ゆっくり振り返ることもなく
いや、
郵便受けの鍵を失くしても
探そうとせずに来た。
空き缶に溜めた写真を整理しながら想う。
このまま
忘却の淵へ流し込み
頭(こうべ)を上げようと。

-020c4.jpg)